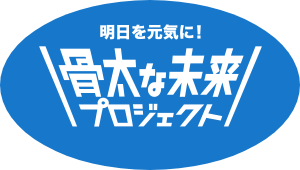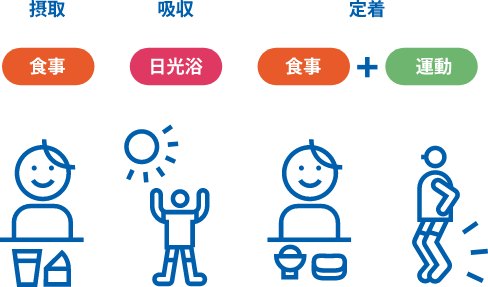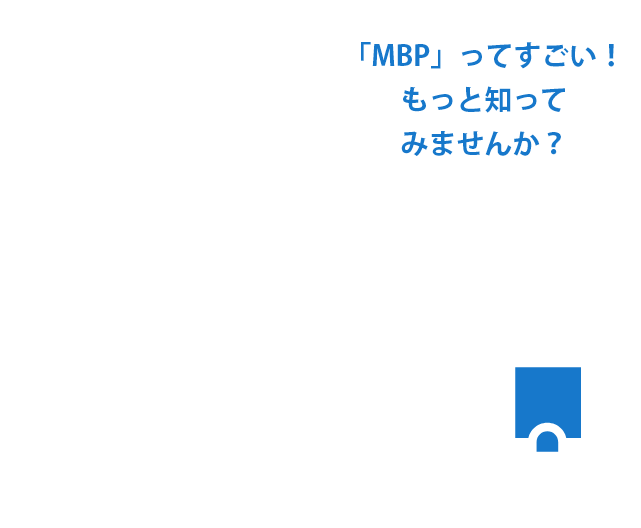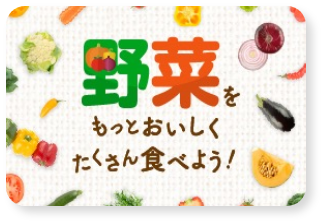強い骨を保つために欠かせない「カルシウム」。カルシウムが多い乳製品の中でも、チーズは手軽に、かつ効率良くカルシウムが摂れる優れた食品です。そこで今回は、カルシウム含有量が多いチーズをランキング形式でご紹介。骨を強くするために、最適なチーズの選び方、より効果的に栄養を摂り入れる方法について解説します。
チーズが骨に良い理由!知られざるチーズのパワー

チーズは、牛や羊のミルクなどを原料にして発酵・熟成された乳製品です。カルシウムやたんぱく質、ビタミンAやB2、リンなどのミネラルといった骨の健康に重要な成分が凝縮されています。野菜や魚などに比べて、チーズはカルシウム吸収率が高いことも特長です。
また発酵食品であるチーズは、発酵の過程で腸内環境を整える成分が生成され、さらにカルシウムの吸収を高める働きも期待できます。
このように、チーズはカルシウムだけでなく、骨の健康に役立つさまざまな栄養素が含まれており、強い骨を保つために一役買ってくれる心強い食材なのです。種類によって少量でも豊富なカルシウムを含んでいるもの、「MBP」入りのもの、カルシウムの吸収を助けるビタミンD入りのものなどがあり、効率よく栄養補給ができます。
カルシウムが多いチーズランキング

日本でもよく知られていて買いやすいチーズの中から、100gあたりのカルシウム含有量が高い種類をランキング形式でまとめたものが以下です。
参考:文部科学省「食品成分データベース」
1位:パルメザンチーズ (100gあたり約1300mg)
日本ではよく粉チーズとして使われていることが多い硬いチーズです。少量でもカルシウムを効率的に摂取できます。
2位:エメンタールチーズ (100gあたり約1200mg)
丸い大きな穴が開いているのが特徴のスイスのチーズ。チーズフォンデュやサラダなどに使われます。
3位:チェダーチーズ (100gあたり約740mg)
ハードタイプで濃厚な味わいが特徴のイギリス生まれのチーズです。色は薄い黄色からオレンジで、おつまみチーズとしてもよく見られます。
4位:ゴーダチーズ (100gあたり約680mg)
セミハードタイプのオランダのチーズです。柔らかい食感とマイルドでクセのない味わいはどんな料理にも合い、日本でも人気です。
5位:プロセスチーズ (100gあたり約630mg)
ミルクから作られるナチュラルチーズに対して、ナチュラルチーズを加工して作られたのがプロセスチーズ。日持ちがするのが特徴で、日本やアメリカでよく消費されています。
6位:ブルーチーズ (100gあたり約590mg)
青カビを繁殖させて熟成したチーズで、独特の香りと風味、強い旨味と塩気が特徴です。
7位:カマンベールチーズ (100gあたり約460mg)
なめらかでクリーミー、ミルクの旨味が詰まった優しい味で、柔らかいチーズの中では最も親しまれている種類です。
チーズのカルシウムをより効果的に摂るコツ
カルシウムの吸収という点からは、食べ合わせを少し意識するのがおすすめ。そのまま食べるより、効果的に栄養を摂ることができます。
<チーズと一緒に摂りたい食品>
・ビタミンDを含む食材…ビタミンDはカルシウムの吸収を助けてくれる代表格。魚介類、キノコ類に多く含まれています。特に、鮭、イワシの丸干し、秋刀魚。きのこなら、きくらげ、干しシイタケなどが良いでしょう。
・マグネシウムが豊富な食材…マグネシウムはミネラルの一種で、骨の健康や身体の代謝に欠かせません。あおさやワカメなどの海藻類、がんもどきや絹ごしなどの豆類、ほうれん草やナッツなどに多く含まれています。
・発酵食品…発酵食品同士を組み合わせることで、栄養価はよりアップし腸内環境を整える作用が高まります。キムチ、納豆、ヨーグルト、甘酒、味噌など、どれも相性はばっちりです。
カルシウムを補うなら手軽なチーズがおすすめ
和食メインの日本人の食事では、つい摂取量が不足しがちのため、常にプラスしておきたいのがカルシウムです。そのままでもおいしく、調理しても和洋中どんな料理にも合うチーズは、カルシウム補給に欠かせません。料理の仕上げに、いつものレシピにと、毎日の食卓に積極的にチーズを取り入れていきましょう。