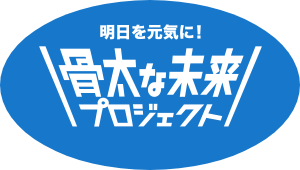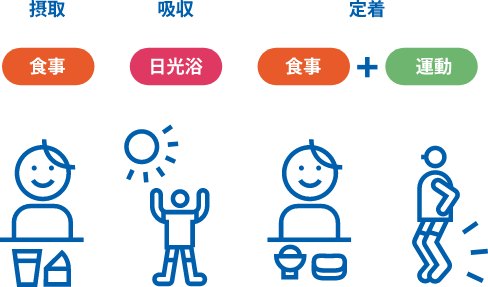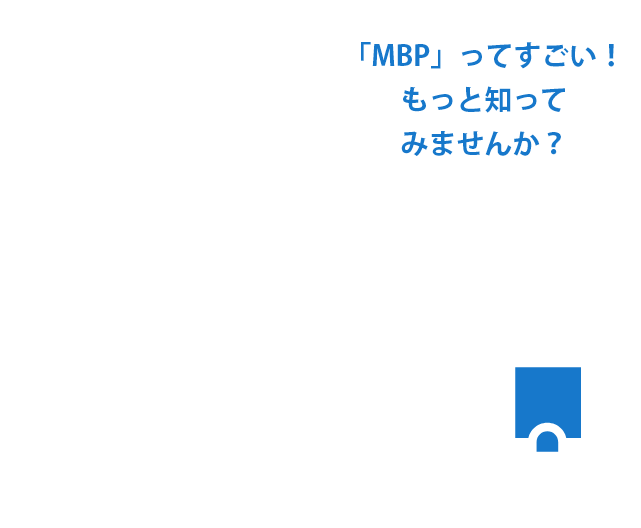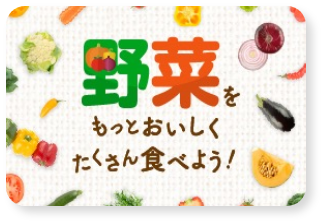骨とよく似てカルシウムを主成分としている、歯。色や硬さや質感が近いため、歯は骨の一部のように思えますが、成分や構造、役割は大きく違います。とは言え、歯と骨の健康状態には密接な関係があるのです。この記事では、歯と骨の違い、歯と骨密度がどう関わっているのかについて解説します。
歯と骨はどう違う?

白くて硬い「歯」と「骨」は、私たちの身体を支えるために大切な組織です。形状は似ていますが、それぞれの成分や構造、機能は次のようになっています。
【歯】
歯は、口の中から見える「歯冠部」と、歯茎の中に隠れていてあごの骨に埋まっている「歯根部」という2つに分けられます。見えている歯(歯冠部)の部分は、表面がエナメル質、その下に象牙質、歯髄という神経があり、エナメル質は人体の組織の中で最も硬く、主にカルシウムやリン酸などの無機質でできています。歯は、モノを噛むのが最も重要な役割です。
【骨】
骨は、「皮質骨」という硬い層、その中に「海綿骨」、「骨髄」という組織があります。成分は約30%がコラーゲンで、約70%がカルシウムやリン酸などの無機質で構成されています。骨は身体全体を支えるとともに、内臓を守る役割を果たしています。
歯と骨の決定的な違いは、再生能力の有無です。歯は再生能力がないため、折れたり欠けたりしても、自然にくっついて治る、生まれ変わるといったことはありません。そのため、虫歯で炎症が起こる、穴が開いてしまうなどすると、人工的なものを詰める治療が必要になります。
一方、骨は再生能力があるため、損傷すると新しい細胞をつくり、自ら修復させることができます。
骨密度の低下は、歯にはどんな影響がある?
骨の強度を示す骨密度は、高いほど骨は強く、低いほど骨は弱いという骨の強度の指標になるものです。骨の強度が低くなった状態を骨粗しょう症とよび、骨折のリスクが高くなっている状態をさします。骨密度が低下すると、実は歯にも影響を及ぼす可能性があります。
歯は「歯槽骨」と呼ばれるあごの骨で支えられています。この骨が強く丈夫だと、歯がしっかりと固定され、噛む力がしっかりと安定的にキープできます。しかしながら骨密度が低下すると、この歯槽骨が弱くなって骨が収縮することがあるため、生えている歯がグラグラと不安定になってしまうことがあるのです。
歯周病と骨粗しょう症には密接な関係も!

また歯周病と骨粗しょう症にも関係があります。
歯周病は、細菌感染によって歯や歯ぐきに炎症が起こる病気です。日本人の約8割が発症しているとも言われているほど身近な病気ですが、厄介なのが初期段階ではほぼ自覚症状がないというところ。進行すると歯ぐきが腫れ、出血や膿が出てきて、最悪歯を抜かなければなりません。
さらに歯槽骨に炎症が起こると、骨が溶けて骨の健康に重要な骨代謝が活発に行われなくなってしまうことがあります。必然的に噛む力が弱くなり、食べ物の栄養の吸収率が下がり、ビタミンD・カルシウム不足になり、骨粗しょう症を悪化させる可能性もあります。
逆に、骨粗しょう症が歯周病を悪化させることもあります。骨がもろいと歯を支えている「歯槽骨」が弱くなり、歯周病になった際に抜けやすくなってしまいます。また、骨粗しょう症の原因のひとつである女性ホルモン「エストロゲン」の減少も歯に影響します。エストロゲンは炎症を抑えたり、歯周環境を健康に保ったりする働きがあるため、骨だけでなく歯周病の悪化につながるのです。
骨粗しょう症を予防し、歯の健康を保つために
骨、歯、いずれの健康を保つためには、十分な栄養と運動が不可欠です。逆にアルコールや喫煙はリスクを高めるので、できるだけ避けるようにしましょう。骨がもろくなる骨粗しょう症、歯に炎症が起こる歯周病、どちらも進行するまで分かりづらいというのが難点です。だからこそ、定期的な歯の検診、骨密度の測定を行って健康状態を把握しておくのがおすすめです。