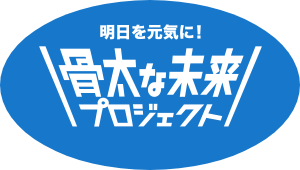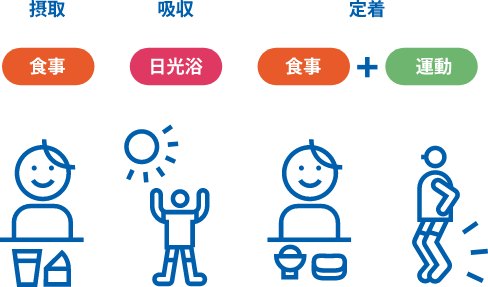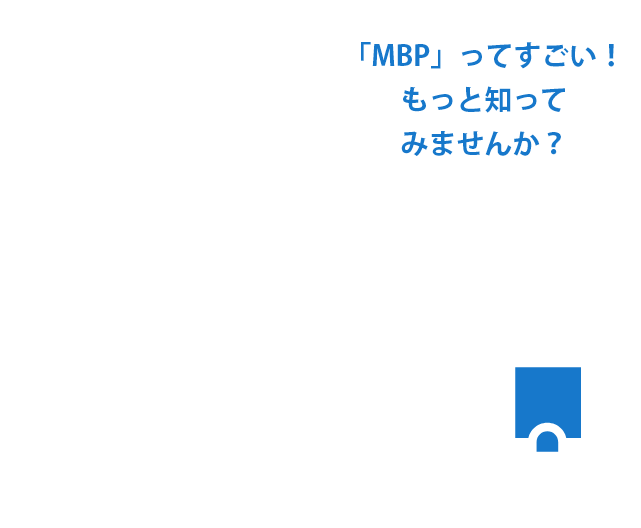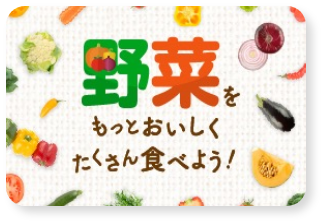骨が「“骨”格」として全身を支える役割をしていることは、広く知られています。また、骨が”カルシウムの貯蔵庫”であることをご存知の方も多いと思います。カルシウムは生命維持のために最も重要なミネラルであり、血液中のカルシウム濃度が低下した場合には、骨からカルシウムを溶かし出し、血液中のカルシウム濃度を一定に保つように調整しています。
病気や肥満の改善に関わる「骨ホルモン」に注目
しかし、骨の役割はこれで全てではありません。最近では、「骨ホルモン」と呼ばれる物質を放出し、全身の代謝を調節する役割を果たすことも明らかとなってきました。その中でも、「オステオカルシン」と呼ばれる骨ホルモンは、生活習慣病の改善や脳の発育や発達など、多くの機能を持つことが報告されており、「若返りホルモン」と呼ばれ大きな注目を集めています。
オステオカルシンは、骨を形成する骨芽細胞から分泌されるたんぱく質です。コラーゲンなどとともに骨の構造を支える支柱としての役割を果たしますが、一部は血液に放出されて全身の臓器に影響を与えます。遺伝的にオステオカルシンを作れないようにした実験動物では、内臓脂肪が非常に多く、血糖値も高くなることから、オステオカルシンは糖質や脂質の代謝に影響を及ぼすと考えられています。
また、この動物は、血糖値を下げる役割を果たすインスリンの濃度が低かったことから、インスリンを作るすい臓とオステオカルシンの関係を調べたところ、オステオカルシンはすい臓に直接働きかけ、インスリンの分泌を促す作用のあることもわかりました。そのため、現在ではオステオカルシンの働きを調節することで、糖尿病や肥満などのメタボリックシンドロームの予防や治療につなげる研究も進められています。
骨の健康は様々な病気の改善につながる可能性が

このように、現在はまだまだ研究段階ですが、「骨ホルモン」はすい臓以外の全身の臓器の機能にも関わっていることがわかってきました。従来、骨は全身を支え保護する役割を持つ縁の下の力持ちのような存在であると考えられてきましたが、近年、骨の概念が大きく変わりつつあります。骨を健康にすることは、単に骨粗しょう症や骨折を防ぐだけではなく、糖尿病をはじめとした様々な病気の改善につながっていく可能性があると言えます。
「骨ホルモン」を活性化させるためには、骨密度を高めることが有効です。骨密度向上に向けて、日々タンパク質や、カルシウム(牛乳・乳製品、小魚)、ビタミンD(魚、干しシイタケ)、ビタミンK(納豆、ブロッコリー)、そして「MBP」などの骨密度を高める機能が確かめられている成分の摂取もおすすめです。